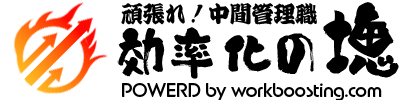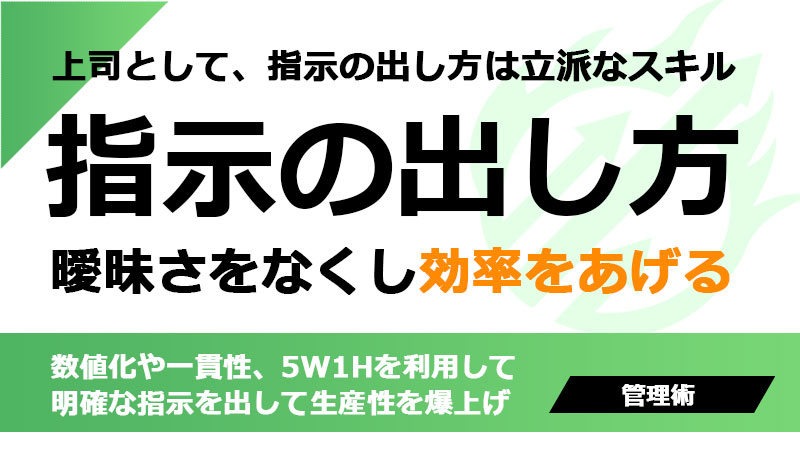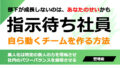こんにちは、ワン太です。
「言ったはずなのに、部下が違うことをしている…」そんな経験はないでしょうか?
中間管理職にとって、指示が伝わらないことは業務の遅延やミスの原因になり、大きなストレスになります。
しかし、これは部下の能力の話ではなく、あなたのせいかもしれません。
本記事では、指示が伝わらない原因を分析し「指示の出し方」の具体的な改善策を紹介します。

指示の出し方を変えれば劇的に業務は効率化します。
指示が伝わらない原因とは?
「言ったはずなのに…」という状況が頻発するのは部下に問題がある場合もありますが、実は指示が曖昧だったり、期日を明確に決めていなかったりと、実は伝え方に問題があることのほうが多いのです。
そこでここでは、指示が正しく伝わらない具体的な理由と、数値化による改善策を解説します。
1. 指示が曖昧(抽象的すぎる)
「なるべく早く」「適当にまとめて」「きれいに仕上げて」といった指示は、人によって解釈が異なります。
例えば、部下Aにとって「なるべく早く」は2時間以内かもしれませんが、部下Bにとっては翌日までにのつもりかもしれません。
これが認識のズレや遅延を生み、ひいてはミスの原因となります。
改善策
- 例:「なるべく早く対応して」→「今日の17時までに対応してほしい」
- 例:「まとめておいて」→「A4一枚にまとめて」
期限や数量を明確にすることで、部下やチームの判断基準を統一することができます。
2. 伝え方に一貫性がない
ある調査によると人が聞いた情報の約50%は1時間以内に忘れ、1日後には70%を忘れると言われています(エビングハウスの忘却曲線)。
日常業務であればよいですが、重要な内容であれば必ず「口頭+文書化」して伝えることが大切です。
改善策
- 口頭指示のみの場合、1日後に70%忘れる → 重要な指示は必ず文書化
- OK例:「この内容はメールにも送るので、必ず後で確認して」
口頭+メールやチャットでダブルチェックすると、記憶違いを防げます。
3. 指示の意図が伝わっていない
「何のためにやるのか」という背景や目的が伝わっていないと、部下は目の前の作業を単なるタスクとして処理しがちです。
その結果細かい判断ができず、期待と違う成果物が出てきます。
例えば、ある企業の調査によると「目的が明確な業務のほうが、作業の正確性が約30%向上する」とのデータもあります。
改善策
- NG例:「お願いした資料を作っておいて」
- OK例:「お願いした資料は、明日の役員会議で今後の方針を決めるための重要な資料です。」
- 意図を伝えるフレームワーク:「この作業は、○○のために必要で、△△を考慮して作ってほしい」
意図が伝わると、部下が自分で考えて必要な材料や書き方を判断できるようになります。
4. 理解の確認をしない
「わかりました」と返事をしたものの、実際には理解していないケースが多くあります。
実際、ある企業の社内調査では「わかりました」と答えた部下のうち、約30%が後でやり直しを指示されたというデータがあります。
上司と部下の認識のズレをなくすためには、理解度の確認が必要です。
改善策
- NG例:「大丈夫?わかった?」(部下は「はい」と言いやすい)
- OK例:「どういう作業になるか、簡単に説明してもらえる?」(部下が説明できなければ、理解不足)
理解度の確認を取り入れるだけで、指示ミスが大幅に減る可能性があります。
数値化すれば指示の質が向上する
指示の伝わりやすさは、数値化することで改善点が明確になります。
- 「なるべく早く」ではなく「今日の17時まで」
- 「売上を増やして」ではなく「先月比10%アップを目標に」
- 「議事録をまとめて」ではなく「課題と期限を明記して」
- 「もっと密に連携して」ではなく「週1回30分のミーティングを実施して」
伝え方のズレを防ぐためには具体的な数値を入れて指示を出すことで、業務のミスや手戻りを減らし、チーム全体の生産性を向上させることができます。
2. 伝え方に一貫性がない
指示が正しく伝わらない原因の一つに「伝え方の一貫性の欠如」があります。
上司が伝える内容がその時々で変わると、部下はどの指示を優先すべきか分からなくなり、結果としてミスや混乱が生じます。
以下に、具体的な問題点と改善策を説明します。
1. 指示の優先順位が不明確
業務の指示を複数出したときに、優先順位を決めないと部下は迷います。
考えればわかるだろうと思うのは、経験豊富なあなただからです。
たとえば「この2つの資料を作っておいて」と伝えても、「どちらを先に仕上げるべきか」「どの程度の完成度が必要か」が分からなければ、効率的に進められません。
実際の問題点
改善策
- NG例:「この2つの資料、早めに作っておいて」
- OK例:「Aの資料は今日17時まで、Bの資料は今週中に仕上げてほしい」
- 優先度を「高・中・低」の3段階で明示し、期限を設定する
2. 指示が変更された際の周知不足
業務の進行中に指示が変更されることはよくあります。
しかし変更を伝える相手が一部のメンバーだけだと、情報の不一致が発生します。
特にチーム全体で進める業務では、全員に最新情報が行き渡らないと、異なる方針で作業が進んでしまいます。
実際の問題点
改善策
- NG例:「この部分少しわかりずらいので、もうちょっとわかりやすく書いて」
- OK例:「この部分少しわかりずらいので、グラフや数値(画像等)を使って書いて」
- 変更の際は関係者全員に「変更点・理由・対応策」をセットで共有する
3. 情報共有の仕組みを作る
伝え方の一貫性を保つためには、情報共有のルールを決めておくことが重要です。
例えばチームの指示をすべてメールやチャットなどのツールで管理し、口頭指示の補足もそこに記録するようにすると情報のズレを防げます。
また変更が発生した際は「変更履歴」を残すことで、誰がどのタイミングで修正を加えたのかを把握できます。
実際の問題点
改善策
- NG例:「チャットかメールで適当に連絡する」
- OK例:「指示の内容はチームのLINEで共有し、変更があればスレッド内で通知」
- 指示の記録を「100%」残すルールを徹底し、曖昧な伝達をなくす
一貫性のある伝え方が業務効率を左右する
伝え方に一貫性がないと、部下は指示の優先順位を誤ったり、最新の情報を把握できなかったりして、業務の遅延やミスにつながります。
- 優先順位や期限を数値で明確に伝える
- 変更があったら関係者全員に最新情報を共有する
- 情報共有のルールを決め、変更履歴を残す
これらを徹底するだけで、指示の伝達ミスを減らし、業務の効率化が進みます。
3. 5W1Hを意識して伝える
指示が正しく伝わらない原因の一つに「情報の抜け」があります。
上司は「指示したつもり」でも、部下にとっては「指示されたのかどうか曖昧」と感じることは少なくありません。
そのため「5W1H(Who・What・When・Where・Why・How)」を明確に伝えることが重要です。
しかし日常業務の場合は「Where(場所)」はあまり関係ないことがほとんどだと思います。
必要があれば使うようにしましょう。
これにより、部下が迷わず業務を進められ、ミスや手戻りを減らせます。
1. 5W1Hとは?
チームに指示を出す際に、次の5つの要素を含めることで、相手に明確に伝わります。
必要があればWhere(どこで)も取り入れましょう。
2. 5W1Hが欠けるとミスを生む
5W1Hのどれかが抜けると、以下のような問題が発生します。
3. 5W1Hを活用した指示の具体例
NG例(曖昧な指示)
「報告書をまとめておいて」
OK例(5W1Hを意識した指示)
「田中さんは今月の売上報告書を、明日15時までに作成してください。月次会議で使用するため、前年同月との比較データとグラフを入れて視覚的に分かりやすくしてください。」
このように指示を具体化すると、部下が迷わずに業務を進められ、効率が大幅に向上します。
指示ミスを防ぐために5W1Hを徹底する
5W1Hを意識した指示を出すことで、部下は「何をどうすればいいのか」を明確に理解でき、ミスを減らせます。
特にWhen(期限)とWhy(目的)を明確にすると、部下の優先順位付けや判断がしやすくなり、より適切なアウトプットが得られます。
日常業務で指示を出す際は、5W1Hを意識する習慣をつけるとよいでしょう。
部下のタイプ別・指示の出し方
部下の性格や経験によって、適切な指示の出し方は異なります。
同じ指示でも伝え方を工夫しないと正しく実行されないことがあります。
ここでは、3つの代表的なタイプ別に効果的な指示の方法を紹介します。
経験豊富な部下には「自由度」を持たせる
経験があり、自分で考えて動ける部下には、細かく指示しすぎるとかえって効率が下がります。
指示は「目的」と「期待する結果」を伝え、方法は本人に任せるのがベストです。
新人・不慣れな部下には「具体的に細かく」伝える
経験の少ない部下には手順を明確に示し、参考資料やマニュアルを提供すると、迷わず作業できます。
チェックポイントを設けて、小刻みに進捗を確認するのも有効です。
「この報告書はAフォーマットを使って、過去3ヶ月分のデータを整理してください。途中で確認するので、まず1ページ作成して見せてください」
マルチタスクが苦手な部下には「優先順位を明確に」する
複数の業務を同時進行するのが苦手な部下には、何を優先すべきかを明確に伝え、スケジュールを整理する手助けをするとミスを減らせます。
「この2つのタスクのうち、Aを先に進めて。BはAが終わったらでOK」
指示の出し方を変えれば劇的に業務は効率化する
指示が正しく伝わらない原因は、曖昧な表現や一貫性のない伝え方にあります。
しかし5W1Hを意識して数値化し、さらに「口頭+文書」で補足しつつ、理解の確認を徹底することで、指示のズレは大幅に減らせます。
指示の伝え方を工夫するだけで、業務のミスが減り、チームの生産性が向上します。
伝えた「つもり」ではなく、「伝わったか」を意識し、正しいコミュニケーションを実践することが、中間管理職の大きな役割と言えるでしょう。