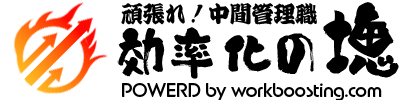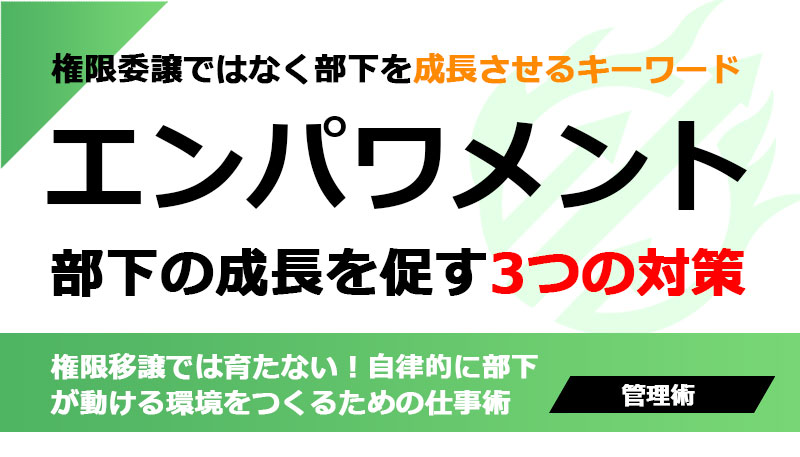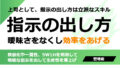こんにちは、ワン太です。
「部下に仕事を振っているのに、なかなか主体的に動かない」
こうした悩みを抱えるマネージャーは少なくありません。
そういった部下に対するマネジメント手法として注目されているのが「エンパワメント」です。
本記事では、部下の主体性を引き出し、チームの力を最大化するための「エンパワメントの実践方法」を解説します。

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、後進の育成にとても重要な考え方です。
エンパワメントとは
エンパワメント(Empowerment)は、1970年代に社会学や福祉の分野で広まり、個人や集団が主体的に行動できるよう支援する概念として注目されました。
その後1980年代以降、企業マネジメントにも導入され、従業員の権限移譲や意思決定の分権化が組織の生産性向上につながると考えられるようになりました。
心理学者アルバート・バンデューラの「自己効力感(Self-efficacy)」の理論も関係しており、「自分に能力があると信じることで積極的に行動し、成果を出せる」とされています。
現在ではビジネス・教育・社会福祉など多分野で活用され、個人の成長や組織の競争力向上に欠かせない考え方となっています。
今、エンパワメントが必要な理由
働き方が多様化し、リモートワークやフラットな組織が増える中、上司の指示を待つだけでは対応しきれない場面が増えています。
変化の激しい時代において、社員一人ひとりが主体的に考え、行動できることが企業の成長には欠かせません。
エンパワメントによって権限が委譲されると、自分の判断で仕事を進められるようになり、自己効力感が高まります。
その結果、モチベーションや生産性が向上し、組織全体の活性化にもつながります。
また、責任を持って仕事に取り組むことで、成長の実感が得られ、離職率の低下にも貢献します。
つまり、エンパワメントは企業の競争力を高めるだけでなく、社員の成長を促す重要なマネジメント手法なのです。
エンパワメントが機能しない3つの原因と対策
エンパワメントがうまくいかない理由の多くは、実は部下側ではなくマネージャー側にあります。
ここでは、エンパワメントがうまくいかないマネージャーに共通する課題とその対策を説明します。
フィードバックと成長の機会の提供
エンパワメントを機能させるには単に任せるだけでなく、定期的なフィードバックを行い、成長の方向性を示すことが不可欠です。
「部下の主体性を尊重しよう」と仕事を振ったまま放置すると、進め方が分からず手が止まる、または成果が期待とズレてしまうこともあります。
改善策:「仕事の意味を伝え、適切な進捗確認を設ける」
- 仕事の目的と期待する成果を明確に伝える(なぜ必要か、どのように活用されるのか)
- 「いつでも相談して」と言うだけでなく、「○日後に進捗を確認しよう」と具体的に決める
NG例:「この資料を作っておいて」
OK例:「この資料は○○社向けの提案用。△△を強調すると効果的だから、まずは構成を考えて○日後に見せてほしい」
放任しすぎず、適度なフィードバックを行うことで、チームメンバーが主体的に考え、責任感を持って行動できる環境を作ることができます。
裁量を与え、細かく口を出さない
マイクロマネジメント(細かすぎる指示)を避け、定期的なチェックインを行いながらも、詳細な指示ではなく、目標や成果の方向性を示すことが重要です。
細かすぎる指示は「結局、マネージャーのやり方に合わせないとダメなのか」と感じ、部下のモチベーションが下がる原因にもなります。
改善策:「やり方」ではなく「ゴール」を示す
- 「何を目指すか」だけを伝え、進め方は部下に考えさせる
- 途中で細かく口を出すのではなく、適切なタイミングでフィードバックを行う
NG例:「このデータは表ではなくグラフにして、色はこのパターンにしてほしい」
OK例:「このデータは、視覚的に分かりやすい形にまとめてほしい。どう表現するのが最適か考えてみてくれる?」
まずは小さなタスクから任せ、徐々に意思決定の幅を広げることで、本人の自信とスキルを育てることが大切です。
心理的安全性を確保する
失敗を許容し、挑戦しやすい環境を整えることで、従業員は積極的に行動できるようになります。
ミスをすると問答無用で叱責されるような職場環境では、誰も積極的な行動を起こす人間はいなくなります。
それは結果として部下の成長機会を奪い、長期的にはチームの成長を妨げることになります。
改善策:「失敗を学びに変える文化」を作る
- ミスが起きても、「何が問題だったか」「次回どう改善できるか」を一緒に考える
- いきなり大きな仕事を任せるのではなく、小さな仕事から成功体験を積ませる
NG例:「ミスしないように慎重にやって」
OK例:「失敗しても大丈夫。最初は試行錯誤しながらやってみて、その後改善していこう」
マネージャーはミスを責め立てるような環境ではなく、ミスを許容し、挑戦を促す職場環境を作ることが大切です。
段階的にチームを成長させる
エンパワメントは部下を成長させつつ、結果的にチーム全体で成果を最大化することを目的としています。
そのため、部下の成長段階や仕事内容に合わせて、段階的に権限移譲を進める必要があります。
段階1:指示型
まずは、小さなタスクから、具体的な指示を与えて任せてみましょう。
この段階では部下は「言われたことをやる」段階です。
仕事の目的や期待する成果を明確に伝え、進め方や期限などの具体的な指示を与えます。
部下は、その指示に従って作業を進めます。
- タスク:顧客へのアンケート結果を集計する
- 指示:「このアンケート結果を、項目ごとに集計して、Excelで表にしてください。締め切りは今週中です。」
- 部下の役割:指示された内容に従い、正確に集計して表を作成する。
段階2:コーチ型
部下が一定の経験を積んだら、徐々に仕事の範囲を広げ、進め方を考えさせるようにしましょう。
この段階では「相談しながら一緒に進める」段階です。
仕事の目的や期待する成果は引き続き明確に伝えますが、進め方や手段については、部下に考えさせ、相談に乗ります。
- タスク:顧客アンケート結果を分析し、改善提案をまとめる
- 指示:「アンケート結果を分析し、顧客満足度を向上させるための改善提案を3つ考えてください。来週の会議で共有しましょう。」
- 部下の役割:データ分析の方法や改善提案の内容を自ら考え、マネージャーに相談しながら進める。
段階3:サポート型
部下が自信を持って仕事に取り組めるようになったら、より大きな仕事や、難易度が高い仕事を任せるようにしましょう。
この段階では「見守りながら任せる」段階です。
仕事の目的や期待する成果は共有しますが、進め方や手段は部下に委ね、必要に応じてサポートします。
- タスク:顧客アンケートに基づいた新サービスの企画
- 指示:「アンケート結果を参考に、顧客ニーズを満たす新サービスを企画してください。予算やスケジュールも考慮して、具体的な計画書を作成してください。」
- 部下の役割:新サービスの企画内容、予算、スケジュールなどを主体的に考え、マネージャーに相談しながら進める。マネージャーは必要に応じてアドバイスやサポートを行う。
段階4:委任型
部下が十分な能力と経験を身につけたら、最終的な判断や意思決定を委ねるようにしましょう。
この段階では「任せて見守る」段階です。
仕事の目的や期待する成果を共有し、権限と責任を部下に委ねます。
部下は自らの判断で仕事を進め、結果に責任を持ちます。
- タスク:新サービスの企画、実行、顧客への提案まで
- 指示:「アンケート結果を踏まえ、顧客ニーズを満たす新サービスを企画・実行し、顧客に提案してください。目標達成に向けた戦略、予算、スケジュール、チーム編成など、すべてお任せします。」
- 部下の役割:新サービスに関する全ての意思決定と責任を持ち、マネージャーに報告しながら進める。マネージャーは最終的な承認を行う。
どの段階においても、部下とのコミュニケーションを密に取ることが重要です。
定期的な進捗確認やフィードバックを行い、部下の成長をサポートしましょう。
また、部下の意見を尊重し、主体性を引き出すような声かけを心がけましょう。
段階的にエンパワメントを進めることで、部下は徐々に自信と能力を身につけ、自立した人材へと成長していきます。
そして、チーム全体が「自ら考え、動く組織」へと進化し、組織の成果を最大化することができるのです。
自ら考え、動く組織のために
指示待ち社員の問題は、単に個人の資質ではなく、職場の環境やマネジメントの在り方に大きく影響されます。
上司の細かすぎる指示や、失敗を許容しない文化は、社員の自主性を奪い、成長を妨げます。
この状況を改善するには、権限移譲を適切に行い、社員が自ら考えて動ける機会を増やすことが必要です。
また、心理的安全性の確保や建設的なフィードバックを通じて、失敗を学びに変え、挑戦しやすい環境を作ることが重要です。
エンパワメントを実践することで、社員一人ひとりが主体性を持ち、組織全体の成長につながります。
マネジメントを見直し、指示待ちから自律型チームへの変革を目指して、ぜひ今日から取り組んでみてください!