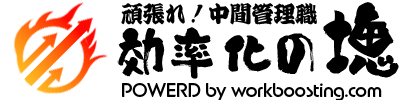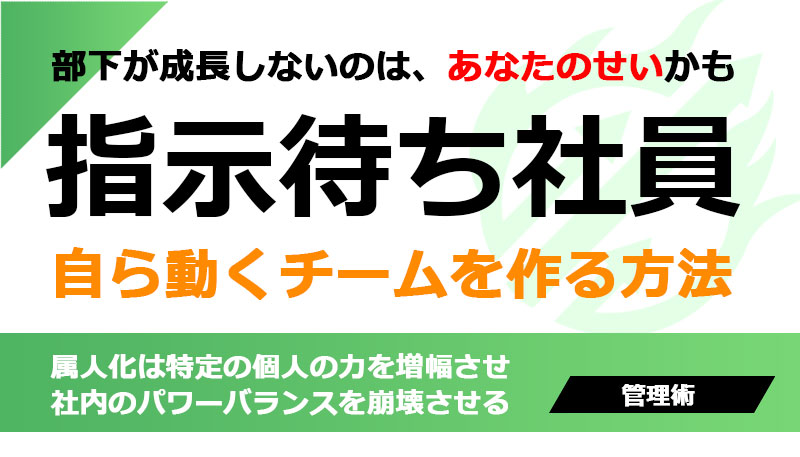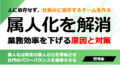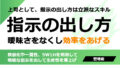こんにちは、ワン太です。
「言われたことしかやらない」「自分で考えて動かない」
このような指示待ちの部下に悩む管理職は多いのではないでしょうか。
部下が自発的に動かないと上司の負担が増え、業務が停滞する原因になります。
しかし指示待ちの姿勢は、単に部下のやる気がないからではなく、組織の環境や指示の出し方に問題があることも少なくありません。
本記事では、指示待ち社員が生まれる原因を分析し、自ら考えて動くチームに変えるための具体的な方法を紹介します。

部下が「動かない」のではなく、あなたの指示が悪く「動けない」、のかもしれません。
1. 「指示待ち社員」が生まれる原因とは?
指示待ち社員は、単なる個人の性格や能力の問題ではなく、組織の環境や上司の指示の出し方が影響していることが多いのです。
ここでは指示待ちの部下が生まれる主な原因を4つに分けて解説します。
①指示待ち社員が生まれる原因
指示待ち社員は、個人の性格や能力ではなく、組織の環境や上司の指示の出し方が影響していることが多いです。
特に細かい指示が多すぎる(マイクロマネジメント) や 上司がすべての意思決定をしてしまう ことが原因で、部下は「自分で考える必要がない」と感じ、判断を放棄するようになります。
この状態では、上司の負担が増え、部下の成長も止まってしまいます。
指示が細かすぎると起こる問題
- 部下の成長機会が奪われ、判断力や問題解決能力が育たない
- すべての判断を上司に仰ぐため、仕事の進捗が遅くなる
- 上司の負担が増え、業務が回らなくなる
解決策:指示の出し方を変える
- 「目的」と「期待する成果」を伝え、方法は部下に任せる
- NG:「この資料はこのフォーマットで、色は青、グラフは3つ入れて作って」
- OK:「この資料は役員向けなので、見やすくまとめてほしい。レイアウトは任せる」
- 判断基準を示す:「何か判断に迷ったら、A社のレポートを参考にするといい」
- 最初は任せつつ、途中で確認する:「まず1ページ作ったら見せて。大枠がOKなら続きは任せる」
権限を委譲することで主体性を育てる
上司がすべての意思決定をしていると、部下は「どうせ最後は上司が決める」と考え、自発的に動かなくなります。
少しずつ意思決定を任せることで、部下は自主的に考えるようになります。
効果的な権限委譲の方法
- 小さな判断から任せる
- NG:「クライアントへの提案資料はすべて確認してから送って」
- OK:「簡単な案件は自分で確認して送ってOK。重要な案件だけ相談して」
- 最終決定権を部下に持たせる
- 例:「このイベントの進行スケジュールは任せるから、必要な調整は自分で決めていいよ」
- 失敗しても責めずにフォローする
- NG:「なんでこんなミスをしたの?」
- OK:「次回はどうすればうまくいくと思う?」
② まずは「やり方」ではなく「目的」を伝える
部下が「自ら考え、行動する」ために「なぜこの仕事をするのか」という目的を理解させることが重要です。
上司が部下に作業を指示する際、「このフォーマットを使って」「この手順通りに」といった具体的なやり方から伝えてしまうと、部下は言われた通りに作業するだけで、自ら目的や背景を考える力が育ちません。
例えば「このフォーマットに沿って表を作って、数字はここに入力して、グラフはこう作る」のように指示すると、部下は言われたことをこなすだけで、工夫や改善しようとはしません。
部下が作業の目的を理解していないと、上司が期待する成果物とは異なるものが出来上がったり、細かい修正が必要になったりして、結果的に上司の負担が増えてしまいます。
「目的」を伝えないと起こる問題
- 判断力が育たず、応用が利かない
- 上司の指示がないと動けず、同じような業務でも毎回細かく指示を求めるようになる
- 意図と違うアウトプットが出てくる
- 目的を理解していないと、「とりあえず作業を終わらせる」ことが優先される
- 柔軟な対応ができなくなる
- 予想外の事態が起きたときに、自分で判断せず、上司の指示を待つようになる
「やり方」ではなく「目的」を伝える指示の例
NG例(やり方だけ伝える)
「このフォーマットに数字を入れて、グラフを3つ作成し、売上推移をまとめておいて」
OK例(目的を伝える)
「この資料は役員会議で使うもので、前年との売上比較が一目で分かるようにしてほしい。グラフの使い方は任せるが、変化のポイントが伝わる形にしてほしい」
このように指示すると、部下は「どうすれば役員にとって分かりやすいか?」を考えながら作業を進めるようになります。
目的を伝えるためのポイント
- 「なぜこの仕事が必要か」を説明する
- 例:「この資料は営業戦略を決めるために必要だから、競合との差が分かるように」
- 「やり方」ではなく「期待する成果」を伝える
- 例:「顧客が見てすぐに理解できる資料にしてほしい」
- 「この仕事で何を達成したいか」を考えさせる
- 例:「このレポートを読んだ人が何を判断しやすくなると良い?」
目的を伝えれば、部下は自分で考えて動くようになる
やり方を細かく指示するのではなく、「何のためにやるのか?」を伝えることで、部下は指示待ちではなく、自ら考えて行動できるようになります。
上司が細かく手順を指示しなくても、部下が意図を汲んで最適な形に仕上げるようになるため、最終的には業務の質とスピードが向上します。
③失敗を許容し、フィードバックを重視する
指示待ち社員が生まれる大きな要因の一つが「失敗を許さない職場環境」です。
部下が「ミスをしたら怒られる」「評価が下がる」と感じていると、自発的な行動を避けるようになります。
結果として「指示を待つのが一番安全」という心理が働き、積極的に動かなくなります。
しかし失敗は成長の機会でもあります。
部下の自発性を引き出すには、ミスを責めるのではなく、適切なフィードバックを与え、次に活かせる環境を作ることが重要です。
失敗を許容しないと起こる問題
- 部下が挑戦しなくなる
- ミスを避けるために、上司の指示を待つようになる
- 「自分で判断すると怒られるから、指示されたことだけやろう」と考える
- 成長の機会が失われる
- 失敗から学ぶことができず、いつまでも同じレベルの仕事しかできない
- 仕事のスピードが落ちる
- すべての決定を上司に仰ぐため、業務が遅れる
失敗を許容し、部下を成長させるための方法
1. 「なぜダメだったのか」ではなく「どう改善できるか」を考えさせる
失敗を責めるのではなく、次にどうすれば成功するかを考えさせることで、部下の成長を促す。
NG例(責める指示)
「なんでこんなミスをしたんだ?」OK例(成長を促すフィードバック)
「何が原因だったと思う?次回はどうすれば防げる?」
2. 小さな失敗は許容し、学びの機会にする
- 「大きなミスを防ぐために、小さな失敗は経験として必要」と伝える
- 失敗しても大きな問題にならないタスクから挑戦させる
例「この企画案、一度君のアイデアでまとめてみて。多少間違えても大丈夫だから、まずはやってみよう」
3. フィードバックは「具体的」に伝える
抽象的な指摘ではなく、何が良くて何を改善すべきかを明確に伝える。
NG例(曖昧なフィードバック)
「もっとしっかりやって」
OK例(具体的なフィードバック)
「プレゼンの資料は良かったけど、グラフの説明をもう少し分かりやすくすると、相手に伝わりやすくなるよ」
4. 失敗を報告しやすい環境を作る
部下がミスを隠すと、問題が拡大する可能性がある。
小さなミスのうちに対策できるよう「ミスしても報告しやすい雰囲気」を作る。
例「もし何かミスがあっても、すぐに相談してくれればフォローできるから、気づいた時点で教えてね」
失敗を許容し、成長の機会に変える
指示待ち社員を減らすためには「ミスを恐れずにチャレンジできる環境」を作ることが重要です。
失敗を責めるのではなく、フィードバックを通じて改善点を伝えることで、部下は自ら考え、成長できるようになります。
④成果を認め、小さな成功を積み重ねる
指示待ち社員を自発的に動ける人材に育てるには、成功体験を積み重ね、自己肯定感を高めることが重要です。
部下が「自分で考えて行動したことが評価される」と感じると、積極的に動くようになります。
しかし成果が認められないと「どうせ頑張っても評価されない」と思い、指示待ちの姿勢が強くなります。
成果が認められないと起こる問題
- モチベーションが低下する
- 「頑張っても評価されないなら、最低限のことだけやればいい」と考える
- チャレンジ精神が失われる
- 「どうせ認められないなら、新しいことに挑戦する必要はない」と感じる
- 上司の期待に気づけない
- 何が良かったのか分からないため、成長の方向性が見えなくなる
小さな成功を積み重ねる方法
1. 具体的に「良かった点」を伝える
部下の行動を認める際は「頑張ったね」だけでなく、何が良かったのかを具体的に伝えると再現性が高まる。
NG例(曖昧な評価)
「いい感じだったね」
OK例(具体的な評価)
「今回のプレゼン、要点を簡潔にまとめていて分かりやすかったよ。特に、データの使い方が効果的だったね」
→ 良い点を明確にすることで、部下は次回も同じような工夫をしようとする。
2. 小さな成功を認めることで、成功体験を積ませる
部下が「成功した」という感覚を持てるよう、日々の小さな成果を評価する。
例「初めて任せた業務だったけど、しっかりやり遂げたね。次はもっと大きな仕事を任せてみようか」
→ 成功体験を積ませることで、自信がつき、自発的に動けるようになる。
3. 目標を細かく設定し、達成感を得られるようにする
大きな目標だけを設定すると、達成までの道のりが長く、途中でモチベーションが下がることがある。
小さな目標を設定し、クリアするごとに達成感を得られるようにすると、やる気が続きやすい。
NG例(大きすぎる目標)
「このプロジェクトを全部成功させよう」
OK例(段階的な目標)
「まずは資料作成を仕上げて、次のミーティングで発表してみよう。その後、クライアント対応も任せていくね」
→ 目標を細分化すると、達成感を得ながら成長できる。
4. 成果を上司だけでなく、チーム内で共有する
個人の成果をチーム内で共有すると、部下のモチベーションがさらに向上する。
例「今回のプロジェクトで、◯◯さんの工夫のおかげでスムーズに進んだね。みんなも参考にしてみて」
→ チームからの承認を得ることで、さらに自発的に動くようになる。
成功体験を積み重ねることで、指示待ちから脱却できる
部下が「頑張ったことが評価される」と感じることで、次の挑戦への意欲が生まれます。
小さな成功を積み重ねることで自信をつけ、自ら考え行動できるようになります。
上司は「どこが良かったのか」を具体的に伝え、成長を促すフィードバックを行うことで、指示待ちの社員を「自ら動ける社員」に育てることができます。
指示待ち社員を自ら動ける人材に変えるために
指示待ち社員が生まれるのは、部下の能力や意欲だけでなく、上司の指示の出し方や組織の環境も影響しています。
細かすぎる指示や失敗を許さない職場では、部下は「指示されたことだけをやるのが安全」と考え、自発的に動かなくなります。
これを改善するには「目的を伝える」「権限を委譲する」「失敗を許容する」「成果を認める」ことが重要です。
上司が適切にサポートしながら、部下が自分で考えて行動できる機会を増やすことで、指示待ちから脱却し、自律的に動けるチームを作れるよう頑張りましょう!