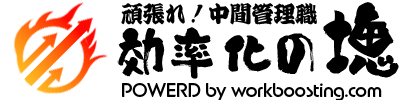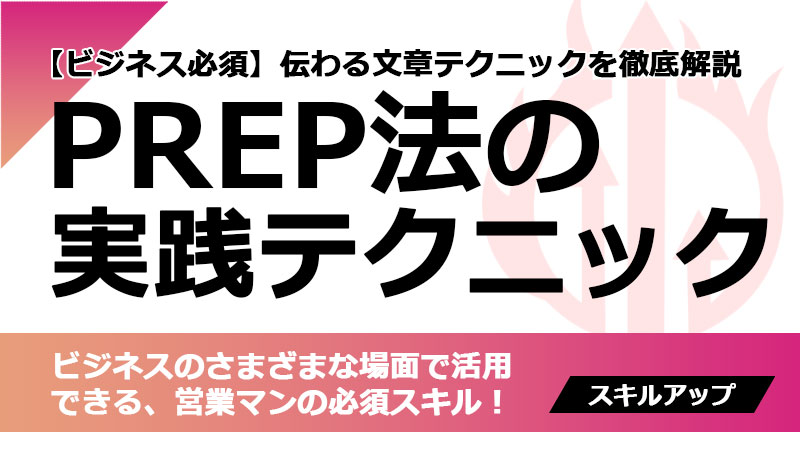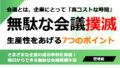仕事でメールを書いたり、企画書を作ったり、プレゼンをしたり…。
「相手に自分の考えがちゃんと伝わっているだろうか?」と不安になることはありませんか?
相手に分かりやすく、かつ説得力のある文章を書くのは、簡単そうで意外と難しいものです。
そんな悩みを解決してくれるのが「PREP法」です。
この記事ではPREP法のメリットや使い方、具体的な事例などを詳しく解説していきます。

この型にはめれば、あなたの言いたいことが相手にしっかり伝わる文章が作れます。
PREP法とは?
PREP法とは、話や文章を構成するためのフレームワークで、以下の4つの要素で構成されています。
- P(Point):結論 最初に伝えたい主張や提案を明確に述べます。 話のゴールを最初に示すことで、聞き手や読み手は内容を把握しやすくなります。
- R(Reason):理由 結論を支える理由を説明します。ここでは、聞き手が納得できるような論理的な根拠を述べることが重要です。
- E(Example):具体例 理由を具体的な事例やデータで裏付けます。 具体的なエピソードやデータを示すことで、説得力が増します。
- P(Point):結論の再確認 最後に、再度結論を述べて全体をまとめます。これにより、話がブレずに明確な印象を残せます。
この順番で話を進めることで、聞き手や読み手は内容を理解しやすくなり、説得力も増すとされています。
特に、ビジネスシーンでのプレゼンテーションや報告、メール、ブログ記事など、様々な場面で活用できます。
なぜPREP法が有効なのか?
PREP法が有効な理由は、人間の思考プロセスに合致しているからです。
結論を最初に提示する
人は最初に結論を知りたがる傾向があります 。
PREP法では、最初に結論を提示することで、聞き手は話の全体像を把握しやすくなり、その後の説明をより理解しやすくなります。
理由と具体例で説得力を高める
単に結論だけを述べるだけでは、相手は納得しないことがあります。
PREP法では、結論の後に理由と具体的な事例を示すことで主張の根拠を明確にし、説得力を高めることができます。
これにより相手は「なるほど、そういうことか」と納得しやすくなります。
シンプルな構成で理解を促進
PREP法は、4つの要素で構成されたシンプルなフレームワークです。
このシンプルな構成により、聞き手や読み手は話の筋道を追いやすく、内容を理解しやすくなります。
また、話す側も構成を組み立てやすいため、よりスムーズなコミュニケーションが可能になります。
記憶に残りやすい
最後に再度結論を述べることで、相手の記憶に残りやすくなります。
最初の結論から時間が経過しても、最後の結論によって話の内容が再び想起され、理解が深まります。
PREP法を使うメリット
PREP法を使うことで、以下のような多くのメリットが得られます。
- 構成がシンプルで分かりやすい: 聞き手や読み手が混乱せずに話を理解できます。
- 説得力が高まる: 理由と具体例をセットで伝えるため、主張の信頼性が向上します。
- 様々な場面で活用できる: プレゼン、メール、ブログ記事、営業トークなど、幅広いシーンで活用可能です。
- 短時間で効率的に伝えられる: シンプルな構成のため、話が長引くことなく、要点を絞って伝えられます。
- 論理的な思考力が身につく: PREP法を意識して文章や会話を構成することで、論理的な思考力が養われます。
- 相手の疑問を解消できる: 結論、理由、具体例という順序で話すことで、相手が抱くであろう疑問を先回りして解消できます。
PREP法を使う際の注意点
PREP法は非常に有効なフレームワークですが、使う際に注意すべき点もあります。
- 理由を論理的に整理する: 理由が曖昧だと説得力が欠けるため、事前にしっかりと準備しましょう。感情的な言葉だけでなく、客観的な根拠を示すことが重要です。
- 具体例は簡潔に: 具体例が長すぎると主張がぼやけてしまいます。ポイントを絞って簡潔に伝えましょう。ダラダラと長い具体例は、かえって分かりにくくなることがあります。
- 再確認はシンプルに: 結論を繰り返す際は、要点を簡潔にまとめることが大切です。長々と結論を繰り返すと、かえって冗長な印象を与えてしまいます。
- 結論のずれに注意: 最初と最後の結論は必ず同じ内容にしましょう。結論がずれてしまうと、話の焦点がぼやけてしまいます。
- 具体例を充実させる: PREP法において、最も重要なのは「具体例(E)」の部分です。ここをどれだけ具体的に説明できるかで、あなたの思いがしっかり伝わるかどうかが決まります。
PREP法の具体的な使い方
この章ではPREP法のさまざまな場面での具体的な使い方を例で説明します
① ビジネスメールでのPREP法の活用
Point(結論): 週次ミーティングの開始時間を10分前倒しします。
Reason(理由): 最近、会議の時間が押してしまい、他の業務に影響が出ているためです。
Example(具体例): 先週のミーティングでは、開始が遅れたことで、重要な議題の議論時間が短縮されました。
Point(再確認): つきましては、次回より9:50開始としますので、ご確認ください。
② プレゼンテーションでのPREP法の活用
Point(結論): 新製品の導入により、売上が20%増加すると予測されます。
Reason(理由): 既存顧客の需要が高く、競合商品よりも機能面で優れているためです。
Example(具体例): 市場調査によると、85%のユーザーが当社の新機能を魅力的だと回答しています。
Point(再確認): この結果から、新製品は売上向上に大きく貢献すると考えられます。
③ クライアントへの提案書でのPREP法の活用
Point(結論): 貴社のコスト削減には、クラウドシステムの導入が有効です。
Reason(理由): 現在の運用では、サーバー維持費が高く、人的リソースも消費しているためです。
Example(具体例): 当社のクライアントA社では、クラウド化により年間30%のコスト削減に成功しました。
Point(再確認): ぜひクラウドシステム導入をご検討いただき、さらなるコスト削減を実現しましょう。
④ 上司への報告書でのPREP法の活用
Point(結論): 来月の営業戦略として、SNS広告の活用を提案します。
Reason(理由): 既存のチラシ広告ではリーチが限られており、新規顧客の獲得が伸び悩んでいるためです。
Example(具体例): 競合B社は、SNS広告を導入したことで問い合わせ数が1.5倍になりました。
Point(再確認): この結果から、SNS広告を活用し、より多くの新規顧客を獲得することが重要です。
⑤ チーム会議でのPREP法の活用
Point(結論): プロジェクトの進行管理をタスク管理ツールに統一するべきです。
Reason(理由): 現在のエクセル管理では、タスクの進捗確認が煩雑で、更新漏れが発生しやすいためです。
Example(具体例): 他部署のXチームでは、タスク管理ツールを導入した結果、進捗確認の時間が30%削減されました。
Point(再確認): 以上の理由から、タスク管理ツールを導入し、チーム全体の業務効率を向上させましょう。
PREP法をさらに効果的にするためのテクニック
PREP法をさらに効果的にするために、以下のテクニックを意識してみましょう。
- 具体的な数字やデータを用いる: 具体例の中で、可能な限り具体的な数字やデータを用いることで、説得力を高めることができます。
- 接続詞を効果的に使う: 接続詞を適切に使うことで、文章の流れをスムーズにし、読みやすさを向上させることができます。
- 逆接の接続詞: 前の文と後の文が反対の関係にある場合に使う(例:しかし、だが、けれども) 。
- 並列の接続詞: 前の文と後の文が同等の関係にある場合に使う(例:そして、また、さらに)。
- 抽象的な表現を具体的にする: 抽象的な表現を具体的な言葉で言い換えることで、相手にイメージを伝えやすくすることができます。
- 聞き手や読み手を意識する: PREP法を使う際には、常に聞き手や読み手がどのような情報を求めているかを意識しましょう。
AI時代におけるPREP法の重要性
近年、AIの進化により、文章作成やコミュニケーションのあり方が大きく変化しています。
しかしAIが生成する文章は、必ずしも正確で分かりやすいとは限りません。
また、AIは感情に訴えかけたり、個々の状況に合わせた柔軟なコミュニケーションを得意としていません。
PREP法は人間の思考プロセスに基づいたフレームワークであるため、AIが苦手とする部分を補完し、より人間味のあるコミュニケーションを実現することができます。
AIを活用する際にもPREP法を理解しておくことで、AIが生成した文章をより効果的に編集したり、修正したりすることができます。
AIが進化しても人間同士のコミュニケーションの本質は変わりません。
PREP法を使いこなすことでAI時代においても、あなたの言葉がより多くの人に伝わり共感を呼ぶことができます。
PREP法まとめ
PREP法は文章や会話を分かりやすく、説得力のあるものにするための強力なツールです。
ビジネスシーンだけでなく、日常会話や自己PRなど幅広い場面で活用できます。
PREP法をマスターすることで、あなたのコミュニケーション能力は飛躍的に向上するでしょう。
ぜひ今日からPREP法を意識して「伝える、伝わる」ことで効率的な業務を実現してください!